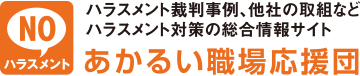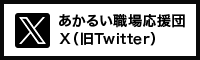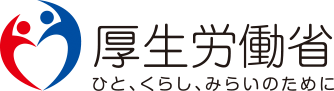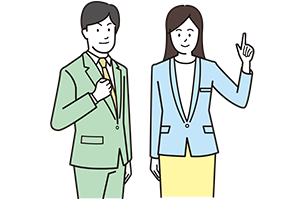【第10回】
必要な指導はしなければならない。だからパワハラ対策。 ―大手建設会社であるB社
| 取組のポイント | 所在地 |
東京都 |
|---|---|---|
|
業種 |
建設業 |
| 従業員数 |
約8,500人 |
大手建設会社であるB社。建設業という仕事柄、注意を怠ると生命の危険もあることから、業務の中で厳しく指導をしなければならない場面もあります。社会的にパワーハラスメントへの意識が高まってくる中で、「本当に必要な指導までがパワハラと誤解されてはいけない」という観点からパワーハラスメント対策に取り組んでいるとのことです。活動の推進責任者にお話しを伺いました。
「パワハラ」という言葉だけの独り歩きは困る
数年前から社会一般でセクシュアルハラスメントに加えてパワーハラスメントという言葉をよく聞くようになりました。しかし「パワーハラスメント」という言葉だけが独り歩きを始めると、現場の管理者や上司が行う本当に必要な指導までもがパワハラと誤解され、正しい人材育成につながらない可能性があることから、会社として正しいマネジメントはどうあるべきなのか、「パワハラ」とは何なのか、ということを社内でしっかり認識させる必要があると考えて、取組を始めました。
既存のセクシュアルハラスメント防止対策と同様に取り組んだ
すでに、男女雇用機会均等法の規制に基づいてセクシュアルハラスメント防止に関する会社としての方針やルールがありましたので、パワーハラスメントについてもそれに倣いました。
「グループ理念」の下に「グループ行動指針」が定められていますが、その中で、基本的人権・多様性の尊重として、ハラスメントの防止に取り組むことを明記しています。 また、就業規則に「ハラスメント防止条項」を定めるとともに、別途「ハラスメント防止に関する取扱細則」を制定し、「人格否定又は雇用不安を殊更にあおる発言」等禁止事項を具体的に明示し、これらを全社員がイントラネットで見ることができるようにし、周知を図っています。
新入社員にハラスメントに巻き込まれないための研修
職場単位で実施している集合研修やeラーニングによるコンプライアンス研修にハラスメント防止の内容も含めており、年に一度は全社員が研修を受ける形になっています。管理職など役職者については、昇格時等に人権研修を行い、その中でセクシュアルハラスメント・パワーハラスメントについても指導しています。
新入社員に対して、「セクハラやパワハラに巻き込まれないためにはどうするか」という研修を行っています。ここでは、業務上必要な場合には上司が注意や指導をするのは当然で、それが正当に行われる限りパワハラには該当しないことを認識させ、そうした指導を受けた際の態度や対応、仕事に対しての取り組み方などを教えています。これにより、正当な指導を「パワハラだ」と問題視したり、指導を受けた時の対応の悪さからパワハラにエスカレートしたりすることを防ぐ効果を期待しています。
また、ハラスメントの防止やコミュニケーションの大切さをアピールした「いきいきと働くために」というハンドブックを全社員に配布し、啓発に努めています。
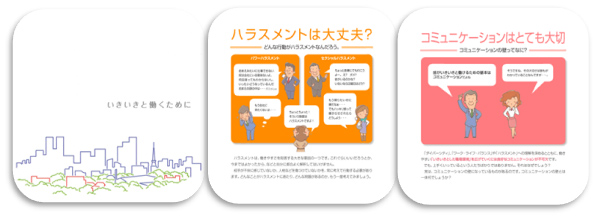
しっかりした相談窓口の体制が安定した活動を支える
社内の相談窓口は、各本部や支店ごとに必ず男女各1名以上の相談担当者を置き、対応しています。相談担当者は各部門の人事担当ですが、ハラスメントについて詳しくない社員もいたので、実際に相談が来た際の対応についての研修をしっかり行い、第一次対応について理解してもらいました。さらに、聴く姿勢、声の抑揚、服装、ヒヤリングのポイントや具体的会話の例などを記載した対応マニュアルを作成しています。これによって相談担当者側の対応のバラつきを無くし、相談する側も安心して話ができる環境も整備しました。相談者としてもきちんと話を聞いてもらえるだけで、心の負担が軽くなり、問題の解決につながる場合もあり、手間暇をかけて担当者への研修やマニュアルを準備したことが良かったと感じています。
パワーハラスメント対策はグレーな部分の対応が課題
パワーハラスメントとはこういうものだ!という明確な定義は難しいものです。「明確にやってはいけないこと」ははっきりしているので、判断が難しいようなグレーな部分をなるべく明確にして管理職に向けて研修を行っています。1回なら問題にならない行為も、何度も行えばハラスメントになったり、指導しているうちにエスカレートしてハラスメントになったりすることもあります。その辺の難しさを上司も部下もお互いに理解し、働きやすい職場になるよう対策に取り組んでいます。
事例をお聞きして・・・
大企業ならではの体制で取り組んでおり、一つ一つのことを着実に定着させています。さらに、研修など、独自に内容を工夫し、それを進化させていく姿勢を持っています。しかし、これは大企業だからできているのではなく、担当の方の意欲と情熱によるものだということが、言葉の端々から伝わってきました。